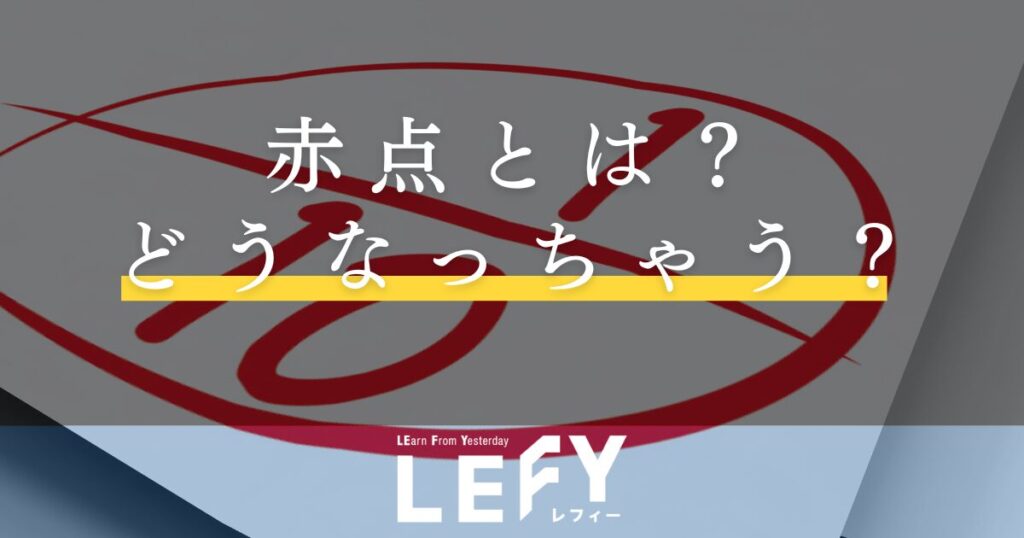学校の定期テストで非常に低い点数を取ってしまい、「赤点かもしれない」と不安になった経験はありませんか?
赤点は学習面だけでなく、将来の進路や学校生活にも影響を及ぼす可能性があるため、軽視できません。この記事では、赤点の基礎知識から具体的な対策法まで詳しく解説し、勉強や進路で失敗しないためのポイントをお伝えします。赤点のリスクや回避のコツをしっかり押さえて、成績を安定させる一助にしてください。
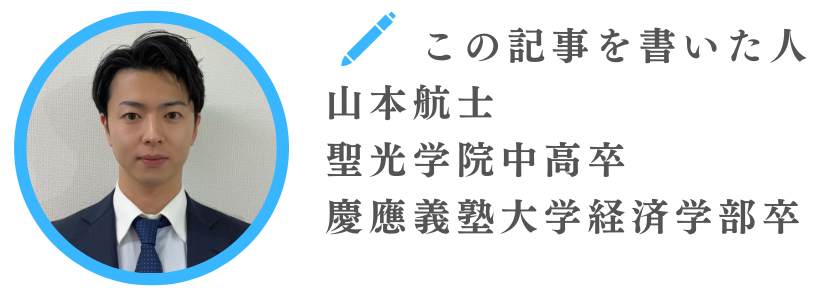
赤点の基本を理解しよう
赤点とは一体何か、どうして学校ごとに基準が違うのかと疑問に思う方もいるかもしれません。
ここでは、赤点の意味と学年による違いを押さえ、まずはその本質を理解することがポイントです。
赤点の現状を知ることで、学習対策の方針が立てやすくなります。
赤点の由来と定義
赤点は、古くから通知表で点数が赤字で書かれたことに由来しています。
学習指導要領で定義された正式な用語ではありませんが、進級基準に達しない点数を指す俗称として一般的に使われています。
基準点は学校によって異なり、平均点の一定割合や、あらかじめ定めた点数が目安になることが多いです。赤点は一度取るだけで成績を大きく下げる原因となり、内申点や評価にも影響します。
赤点は、あくまで教科書レベルの基本事項を落としている可能性が高い点数です。
テスト問題の傾向は基本問題が中心なので、基礎学習の欠如が赤点につながります。数点差で赤点になるケースもあるため、普段からコツコツ勉強しておく必要があります。
赤点と聞くと留年を連想する方もいますが、具体的に留年に結びつくかは学校の規定や学年によって変わります。
義務教育の中学では留年がほぼないものの、私立中高一貫校では内部進学が許可されない例もあり、高校であれば単位不足で留年につながる可能性があります。
中学と高校での違い
中学は義務教育のため、テストの点数だけですぐに進級ができなくなることはほとんどありません。ただし、成績不良が続くと補習や再試験が課されることがあり、内申点が大きく下がると高校入試に影響が出ます。赤点が多いまま放置すると、高校受験の際に希望校をあきらめなければならないケースもあります。
一方、高校は単位制を基本としています。特に全日制高校では学年ごとに一定の単位を取得しないと進級が認められません。赤点で単位が認められない場合、再テストで合格点に到達しなければ留年のリスクが高まります。推薦入試においても、評定平均が大きく下がる原因になります。
中高一貫校の場合は、中学段階の赤点が続くと内部進学が危ぶまれる場合があります。赤点が常態化していると、周囲との差が広がりやすいので、早めに対処することが大切です。
公立と私立での違い
赤点の扱いは学校の運営方針にも関係があり、公立と私立では運用が大きく異なります。ここでは、両者の特徴や中学段階で起こりうる進級リスクなどを中心に解説します。
学校形態を踏まえて赤点対策を行うことが大切です。
公立中学
赤点を繰り返すことで通知表の評定が下がり、公立高校入試で不利になることがあります。実際に定期テストの結果が悪いまま放置すると、合否を左右する内申点が伸びず、志望校を下げざるを得なくなるケースがあるため要注意です。
公立中学は学区によって生徒の学力層が幅広いのが特徴です。補習や追試が用意されることもありますが、自主的に学習を進めないと赤点脱却が難しくなる場合があります。学校が行うサポートをうまく利用しつつ、家での学習習慣を確立することが大切です。
赤点を連発すると、学習への意欲がさらに下がり、悪循環に陥る生徒もいます。早めに基礎を振り返り、学校の課題を丁寧にこなすだけでも大きく変わります。内申点が直接かかわる公立高校受験を見据えて、定期テストの点数を着実に上げる対策をとりましょう。
私立中学

赤点が続くと内部進学を認めてもらえず、高校受験を強いられる場合があります。
私立中学では成績不良が続くと、保護者面談などを通じて公立中学への転校を促されることがあります。
学校によって規定は異なりますが、成績を回復する見込みがないと判断されると厳しい対応を取る学校もあるため、赤点の放置は非常にリスクが高いです。
私立の中高一貫校での学習進度は早く、テストの難度も比較的高い傾向があります。学校特有のテキストや問題集を使用している場合、その対策に合わせた学習が必要です。
赤点が出始めたら家庭教師や個別指導塾など外部のサポートを検討するのが良いでしょう。
赤点が招く4つの悪影響
赤点は一時のテスト結果にとどまらず、多方面に影響を及ぼす可能性があります。進学・卒業・奨学金など、意外なところで足を引っ張ることがあるため、先を見据えた対策が必要です。ここでは代表的な4つの悪影響を取り上げます。
内申点の大幅な低下
赤点を取ると、通知表の評定が下がる可能性が高くなり、全体の内申点にも影響を与えます。
内申点が低いと、高校入試や大学入試の推薦枠を狭める原因になり、進路の選択肢が限られることがあります。
特に中学の評定は公立高校の合否を大きく左右します。
普段の授業態度や提出物が評価されるとはいえ、テスト結果は内申点の主要な要素になるため、赤点が複数科目にわたると大きなマイナスになります。
内部進学/推薦入試で不利になる
指定校推薦や大学附属校での内部進学には「評定○以上」といった設定がされていることが多く、1科目でも低い評定が続くと条件に届かないことがあります。
大学受験における評定平均は高1から高3の初期段階で確定することが多いため、赤点を繰り返していると追いつくのが難しくなります。
奨学金への影響

赤点によって成績が下がると、奨学金の要件を満たせないリスクが高まります。例えば日本学生支援機構では、一定以上の評定平均を条件に挙げる場合があり、赤点を続けると推薦を得られなくなる可能性があります。
将来的に家計面で奨学金が必要になる場合、評価基準を満たせずに給付型を利用できない状態になってしまうことがあります。成績次第で進学費用の負担が増える恐れがあるため、赤点を取らないことは経済面でも重要です。
留年・転校のリスク
高校で赤点が続き、追試や補習でも回復しない場合は単位不足で留年につながる場合があります。
特に難易度の高い学校では、内容に追いつくのが困難になることもあります。
中高一貫校では、成績不良を理由に内部進学が認められず、転校や外部受験を勧められる可能性があります。
留年や転校は大きな負担となり、精神面にも影響を与えるため、早めの対策が欠かせません。
赤点を回避する学習法
赤点を防ぐためには、普段の学習方法が鍵になります。基礎を確実に身につけ、テストで失点しない工夫を行えば、大幅な成績低下は起こりにくいです。ここからは、具体的な勉強法を3つの視点で紹介します。
授業と宿題をフル活用
赤点回避の第一歩は、授業をしっかり聞き、疑問を出来る限り早くで解決することです。
授業中に理解できない点が残ってしまうことは仕方がないことですが、授業が終わったら先生に質問したり、友達に聞いたり、塾の先生に聞くなどして必ず解決しましょう。
宿題においても、わからない問題がある場合は、必ず解決しましょう。基礎的な力を身に着けるために取り組んだ方がよい範囲を宿題として先生が指定していますので、まずは提出物にしっかり取り組むことで学力の定着が期待できます。
基礎重視の演習が鍵
赤点ラインを抜け出すには、応用問題よりもまずは基礎問題を確実にこなすことが効果的です。
数学であれば基本的な計算、英語であれば単語や文法など、まずは落とせない部分を徹底練習するのが重要です。
基礎を固めれば定期テストで大崩れしにくくなり、結果的に赤点を回避しやすくなります。
苦手科目の克服ステップ
赤点になってしまう科目は苦手意識が強いケースが多いです。
苦手科目は、教科書や参考書を使い、基本レベルの内容に何度も繰り返し取り組みましょう。
何度も取り組むと、2回目、3回目にかかる時間は少なくなっていきますし、繰り返す中で、理解が深まっていきます。
自力で取り組むのが難しい場合は学校の先生や塾に相談するなど、早めに周囲のサポートを受けることが大切です。
赤点を取ったときの対処
万が一、赤点を取ってしまっても「もうダメだ」と思わずに、補習や追試などの救済措置を活用しましょう。ここでは、赤点を取った後に何をすべきか、保護者ができるサポートもあわせて解説します。
補習と追試を確実に受ける
多くの学校では、赤点を取った生徒向けに補習や追試を行い、一定の得点を取れば単位や成績が認められるようにしています。赤点を取った際には、こうしたチャンスを逃さず積極的に活用することが重要です。
補習では授業よりも丁寧に基礎を教えてくれる場合が多く、疑問点を解決しやすいです。追試に向けた目標を設定して、苦手箇所を優先的に学習すれば、留年や成績大幅低下を回避できる可能性があります。
保護者ができるサポート
赤点を取った生徒は、自信を失って勉強への意欲が下がりがちです。保護者はまず、生徒の気持ちを受け止め、状況を一緒に整理してあげることが大切です。
必要に応じて学校と連絡を取り、補習や追試のスケジュールを確認し、学習計画を手伝うなど具体的な支援を行うようにしましょう。過度にお子さんを責めるのではなく、次のチャンスをどう活かすかを一緒に考えることが大切です。
まとめ
赤点はテストでの一時的な低評価にとどまらず、内申点や推薦入試、奨学金、進級など多方面に影響を及ぼす可能性があります。公立や私立、中学や高校といった学校ごとに赤点の扱いやリスクは異なりますが、共通して言えるのは「基礎学力の不足」が最大の要因になることです。日々の授業と宿題に真面目に取り組み、基礎演習を繰り返すことで赤点を回避する力が身につきます。
もし赤点を取ってしまっても、学校の救済措置である補習や追試をしっかり活用すれば、挽回できるケースも少なくありません。周囲のサポートを受けて前向きに勉強方法を見直せば、次のテストではより安定した成績を狙うことができます。赤点を恐れるばかりでなく、自身の学習習慣や苦手分野を見直すきっかけにすることが大切です。
中高一貫校生のマンツーマン指導ならレフィーにご相談ください
レフィーの中高一貫校生/定期テストサポートコースでは
- 社会人プロ講師
- 東大、早慶以上の大学生・大学院生講師(かつ難関私立中高一貫校卒)
※さらに、プロ講師、東大早慶以上の大学・大学院生の中からどちらも採用率20%程度
が完全1対1のマンツーマンで指導するため、着実に効果を感じられるはずです。
「せっかく難関中学に入学したのに、中だるみで成績が低迷してしまった…」
「学校推薦を狙いたい!そのために定期テストで高得点を取る必要がある」
中高一貫校生は、ぜひお気軽に当塾レフィーにお問合せください!
通塾生の成績が実際に伸びています。
▼お気軽にお問い合わせください!
(横浜駅徒歩7分。原則対面授業ですが、オンラインをご希望の方はご相談ください)