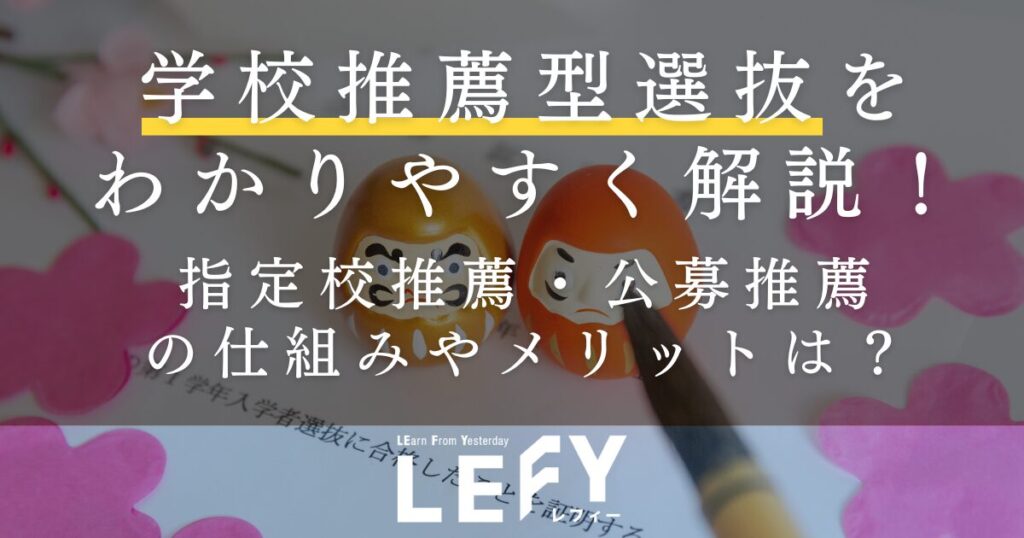学校推薦型選抜は、高校での学習成果や活動実績が重視され、早期合格のチャンスを広げる入試制度です。
併願や不合格時のリスク管理なども押さえながら、最適な進路を見極めましょう。
学校推薦型選抜とは?

学校推薦型選抜のキホン
学校推薦型選抜は、高等学校の校長や担当教員から推薦を受けて出願する大学入試制度の一つです。
一般入試や総合型選抜とは異なり、在学中の成績や高校内での活動実績、人物評価などが大きく考慮される点が特徴です。多面的な視点から受験生を評価するため、筆記試験の点数だけでは測りきれない能力や意欲をアピールしやすい制度になっています。
大学側は、高校での学習態度や生活面での評価が高い生徒を早い段階で確保したいと考えています。生徒側にとっては、高校でコツコツと積み上げてきた成果を合否に反映できるメリットがあります。たとえ筆記試験の負担が少なかったとしても、出願条件において厳しい評定平均や資格要件が定められている場合も多く、一般入試とは別の準備が必要になります。
近年は少子化の影響や大学入学者数の確保などさまざまな背景から、多くの大学で学校推薦型選抜の比率が増えつつあります。早稲田大学や慶應義塾大学などの難関私立大学でも一定数の学校推薦枠を設けるケースが見られます。国公立大学でも推薦枠が拡大する動きがあり、以前よりも多様な入試方式が選択肢として用意されています。
一般入試との違いは?
学校推薦型選抜と一般入試の大きな違いは、高校側からの推薦書や調査書の内容が必須であることです。成績評価では評定平均が非常に重要視され、一定基準を満たしていないと出願資格が与えられない大学もあります。さらに活動実績や人間性、コミュニケーション力など、多角的なアプローチで合否判定が行われることが特徴的です。
一般入試では主に筆記試験や共通テストなどの得点が合否を左右しますが、学校推薦型選抜の場合は高校時代の日常の努力が評価の大部分を占めると言えます。筆記試験を実施しない大学もありますが、近年は文部科学省の方針もあり、推薦枠であっても学力評価のための小論文や基礎的な筆記試験を課す例が増えています。結果的に、学校推薦型選抜を利用する生徒も一定程度の学力対策が必要になっています。
また、学校推薦型選抜では専願扱いになることが多いため、合格した場合は必ずその大学へ進学しなければならないケースが多いです。合格後に辞退すると高校や後輩にまで影響が及ぶ場合があるため、一般入試と比べて進路変更の自由度が低い点に注意が必要です。
近年の制度改革と最新動向
近年の大学入試改革によって「AO入試」が「総合型選抜」に呼称変更されたのと同様に、従来の「推薦入試」も「学校推薦型選抜」という呼び名に変わっています。これに伴い、学校推薦型選抜でも学力を担保するための基礎学力検査や共通テストの利用が推奨されるようになりました。従来のように書類選考と面接のみで合否を決める大学は少なくなりつつあります。
また、新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、オンライン面接を導入する大学が増加しています。遠方から都市部の大学を受験する生徒にとっては移動費と時間を節約できるため、受験しやすい環境が整いつつあると言えます。さらに、指定校推薦や公募推薦の枠を拡大する大学も多く、大学の入学者数確保の意図と生徒の多様なニーズのマッチングが進んでいる状況です。
一方、学校推薦による入学者が増えすぎると大学全体の学力レベルにばらつきが生じるという懸念もあります。そのため、難関大学では学力を検証する試験を積極的に実施し、適性の高い学生を選抜する動きがさらに強まっています。今後も制度改革や社会情勢に合わせて学校推薦の在り方が変化することが予想されるため、受験生は最新情報を入手するようにしましょう。
学校推薦型選抜の種類と仕組み
学校推薦型選抜には「指定校推薦」と「公募推薦」の2つがあります。
指定校推薦の仕組み
指定校推薦は、大学があらかじめ指定した高校に対して推薦枠を付与し、その高校から推薦を受けた生徒が受験できる制度です。多くの場合、評定平均の条件や高校内での選考をクリアした上で推薦されれば、大学側での合格率が非常に高いという特徴があります。高校内での推薦者選抜が最難関になることもあり、同級生との競争が激しいケースもあります。
指定校推薦の仕組みでは、推薦枠のある学部・学科や募集人数があらかじめ決まっているため、学校の進路指導部による選考が厳格に行われることが多いです。推薦枠を獲得すると、大学では書類審査と面接程度の軽い試験で合格を出すことが少なくありません。合格後に入学を辞退すると、次年度以降の後輩がその大学の指定校枠を失う可能性があるため、大きな責任を伴う制度とも言えます。
近年は、指定校推薦でも大学側が簡易的な学力テストや面談を行うケースが増えています。学力格差やミスマッチを防ぐための措置であり、生徒自身もしっかりと基礎学力を維持していなければ入学後に苦労する可能性があることを意識しておく必要があります。
公募推薦の仕組み
公募推薦は、大学が広く受験生に対して募集要項を提示し、それを満たす生徒が出願できる制度です。指定校推薦とは違い、高校がどの大学に指定されているかに関係なく受験のチャンスがあります。多くの場合、評定平均や各種検定試験の成績などの条件をクリアしたうえで、校長の推薦状を添えて出願する形になります。
公募推薦は指定校推薦より受験できる間口が広いため、全国各地から志願者が集まりやすいという特色があります。特に人気大学・有名大学では志願者数が多いため、競争率が高くなる傾向があります。
公募推薦の中には、英語力やスポーツ実績、文化活動実績など特定のスキルを評価する「特別推薦」を設けている大学も存在します。「スポーツ推薦」とう言葉は皆さんも聞き馴染みがあると思いますが、ほとんどの場合は、スポーツ実績を活かした特別推薦のことを意味しています。
なお、公募推薦も専願制の場合が多いこともあり、合格したら辞退が難しい点は指定校推薦と共通しています。
総合型選抜との違い
総合型選抜(旧AO入試)は、高校からの推薦状が不要である点が学校推薦とは異なります。自己推薦に近い形式で受験できるため、評定平均のしばりが比較的緩やかだったり、大学の提示する課題や面接、グループディスカッションなどで積極的にアピールする機会が設けられたりすることが多いです。総合型選抜は秋から冬にかけて複数回実施される場合もあり、出願期間が長めに設定されることが特徴です。
一方、学校推薦型選抜では大学側が「高校が太鼓判を押している生徒」という一定の信頼感を前提に受け入れるケースが多いです。総合型選抜ではそのような保証がない代わりに、本人の持つ実績や将来構想、大学とのマッチング度合いなどを独自の視点で評価します。そのため、自己アピール力と志望理由の明確さが、総合型選抜では一層重要になります。
また、総合型選抜と学校推薦型選抜を併願できる大学もありますが、大学や学部によってルールが異なります。いずれの場合も「早期に志望校の出願要件を確認し、自分に合った制度を見極めること」が大切です。
学校推薦型選抜のメリット!
早い時期に合格を得ることができる
学校推薦の大きなメリットとして挙げられるのは、一般入試よりも早い段階で合格が決まる可能性が高いことです。多くの推薦入試は秋から冬にかけて実施され、年内に結果が出ることが少なくありません。
合格が決まれば、残りの高校生活を心の余裕を持って過ごしたり、学費や住居の準備を計画的に進めたりできます。また、一般入試が本格化する前に合格が得られることで、受験勉強に費やす時間や精神的なストレスを軽減できます。
一発勝負に依存しない安心感
一般入試では当日の試験結果が合否に直結するため、体調不良や緊張など不測の事態で実力を発揮できない場合があるかもしれません。学校推薦型選抜の場合は、高校3年間の評価や日頃の活動、面接など複数の要素を総合的に見てもらえるため、突然の失敗が致命傷になりにくいはずです。
調査書や推薦書などの書類審査では、自分が高校時代にコツコツ積み上げた成績や課外活動の実績が評価対象になります。部活動や生徒会活動、ボランティアなどに打ち込んだ成果を、合否判定に活かせる点は一般入試にはないメリットです。
学校推薦型選抜を選ぶ際の注意点