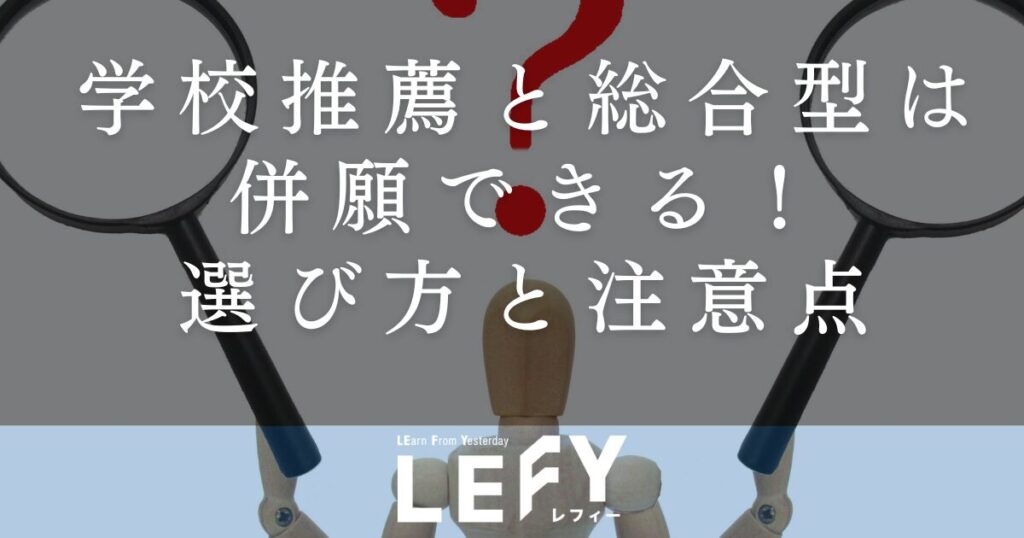学校推薦と総合型選抜には、一般選抜とは異なる独自のルールや評価方法があります。
どちらも早期合格につながる反面、合格後の進学確約を求められる場合があるため注意が必要です。
まずは両方の特徴を押さえておきましょう。
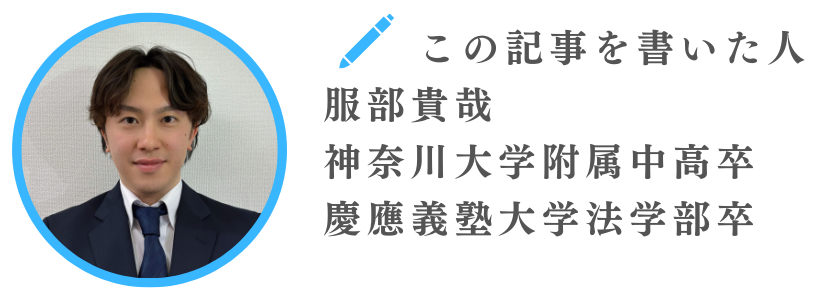
学校推薦と総合型選抜のキホン!
学校推薦の仕組み
学校推薦は、高校と大学の信頼関係をベースに実施される入試方式です。
主に指定校推薦と公募制推薦の2種類があります。
指定校推薦は、大学が特定の高校に対して定めた推薦枠に基づき出願できるため、学内選考を経て推薦資格を得ると合格率が高いことが特徴です。高校の評定平均や日頃の態度・活動実績などが重視され、推薦担当の先生との面談や校内選考が行われることが多くあります。
公募制推薦は、評定平均の基準や小論文、面接といった要件を満たせば、全国どの高校からでも出願できる仕組みです。評定だけでなく面接や課外活動の実績などが合否に影響するため、総合的なアピールが求められる場合があります。
指定校推薦では合格すればほぼ確実に入学する必要があるため、事実上の専願となることが一般的です。
公募制推薦の場合は専願か、併願可かを大学ごとに設定していることが多く、「第一志望とする者」などの文言が要項に記されることもあります。
こうした文言がある場合は合格後の辞退が難しい可能性があるため、併願の可否とあわせて注意深く確認しましょう。
総合型選抜の特徴と評価ポイント
総合型選抜(旧AO入試)は、大学が定めるアドミッション・ポリシーとの適合度を多面的に審査する入試方式です。
学力試験の点数だけでは測れない資質や人間性を評価するため、面接や小論文、プレゼンテーションなど多彩な選考方法が用いられます。
たとえば、志望理由書で大学や学部で学びたい内容を具体的に示したり、高校時代の活動や社会貢献への取り組みをアピールしたりすることが重要です。面接では、コミュニケーション能力や論理的思考力などが評価されるケースが多いです。
総合型選抜では学力だけでなく、課外活動や受賞歴、英語資格試験のスコアなども重視されることがあります。
大学ごとに重視するポイントが異なるため、希望する学部が求める人材像を読み解くことが大切です。たとえば、国際系の学部であればTOEFLやIELTSなどの語学スコアが、教育系の学部であればボランティア経験やリーダーシップの実績が評価されるかもしれません。
また、総合型選抜には「専願」の条件が付く大学と、合格後の進学が必須ではない大学の両方があります。複数の大学に出願する場合は、合格後の辞退が可能かどうかを必ずチェックする必要があります。
併願可能かを決める三つの確認ポイント
ここでは、学校推薦や総合型選抜を複数校で併願する際に見落とせない三つのポイントを紹介します。専願の有無や第一志望の表記、合格後の入学確約など、細かな違いを把握しておくことが合格後の後悔を防ぐうえで重要です。
募集要項の「専願・併願」の定義をしっかり確認する
大学の募集要項には「専願」「併願可」といった文言が記載されており、その解釈が受験計画を大きく左右します。専願と明示されている場合は、合格後に必ず入学することが前提とされる傾向にあります。とはいえ、実際には「専願」と書かれながらも、他大学との併願を完全には禁止していない大学もあります。一方で「併願可」と書いてある大学なら、原則として他大学の受験や合格後の辞退が認められやすいと考えられます。
注意したいのは「合格後は本学への入学を確約できる者」「第一志望とする者」といった記載があるケースです。これらは大学のアドミッション・ポリシーに沿った志望度の高さを求める表現ですが、実際の運用は大学ごとに違います。出願前にQ&Aや説明会で確認し、合格後の入学義務がどの程度強いかを把握することが大切です。とりわけ、専願を徹底している大学に合格すると、他の大学を辞退せざるを得ない可能性があります。
単願と第一志望の違いを理解する
入試要項で目にする「単願」は、基本的にその大学のみを受験するという意味合いが強い表現です。具体的には、合格が出た段階で他大学の受験を取り下げる、あるいは実質的に最初から出願しないことを想定することが多いです。
一方で「第一志望とする者」は、あくまでも大学が求める志望度の高さを示す文言であって、必ずしも他大学を受けられないわけではありません。
ただし「第一志望とする者」という記載であっても、大学によっては合格後の辞退を許可しないケースがあります。入試要項や公式サイトを細かく読み込み、それが事実上の専願に近いのか、それとも一定の条件下で併願を認めているのかを確認しましょう。表面上の言葉だけでは判断しきれない微妙な違いがあるため、わからない場合は大学の入試係に問い合わせるのが確実です。単願と第一志望の違いを誤解すると、進学先を選べなくなる場合もあるので注意が必要です。
合格後の入学確約条件に注意する
併願を考えるときに必ずチェックしておきたいのが、合格後の入学確約条件です。「合格後、本学への入学を確約できる者」という文言がある場合、進学を前提にした合格になるため、後から辞退するとトラブルに発展するリスクがあります。高校との契約上、あるいは大学と高校の信頼関係が崩れる恐れがあり、後輩の推薦枠に影響を及ぼすケースも否定できません。
一方、同じような表記でも、実際には入学手続き締切までは辞退を受け付ける大学も存在します。募集要項や大学のQ&A、説明会のアナウンスなどを照らし合わせて、いつまでに辞退を申し出れば良いのかを調べることが重要です。専願型の学校推薦で合格が決まっているにもかかわらず、総合型選抜や一般入試を続行していると、あとで手続きや入学金の支払いの段階で問題が生じるかもしれません。あらかじめ進路指導担当とも相談し、入学確約の有無を正確に把握しておくようにしましょう。
併願できる大学の募集要項を読むコツ
複数の大学を受けるときは、大学ごとに異なる要項を入念にチェックする必要があります。単なる「専願・併願」だけでなく、評定平均や合格発表日、入学手続期限などを一覧化して比較することで、スケジュールや書類準備の混乱を防ぎましょう。
募集要項で最優先に見るチェック項目
併願を前提に複数の大学を受けるなら、まずは以下の点を優先的に確認するとスムーズです。
第一に「専願か併願可か」の表記を見きわめることが欠かせません。
次に評定平均の条件や英語資格の要否など出願要件を調べ、さらに出願締切、試験日、合格発表日、入学手続き期限を確認します。こうした情報を整理する際には、一覧表形式のメモを作成すると管理しやすいです。
大学によっては、「総合型選抜A方式」「公募制推薦B方式」など、方式ごとに募集要項を分けていることがあります。そのため、志望学部だけでなく、全方式の要項も取り寄せる、もしくは公式サイトから最新情報を入手することが望ましいです。締切や選考内容が異なる場合もあるため、「同じ大学でも複数の入試がある」という点を見落とさないようにしましょう。検討する大学が多いと混乱しがちですが、早期に資料をそろえれば、対策の計画を立てやすくなります。
専願表現のバリエーションを理解する
「専願」「単願」「第一志望とする者」「合格後の入学を確約する」など、専願を示す表現は大学によって書き方がまちまちです。これらはすべて同じ意味ではなく、合格後の辞退を認めるかどうかや、他大学を受けることを禁止する度合いが異なります。たとえば「単願」は他校の出願を想定しないほど厳しい場合が多く、「合格したら必ず入学する」という意図が強いです。
一方で「第一志望とする者」は、単に大学側が志望度の高い受験生を求めている可能性を示すにとどまる場合もあります。結局は、大学のQ&Aや説明会でのアナウンスを確認し、実質的に辞退が許されるかを調べないと誤解を生みやすくなります。特に私立大学は「専願」と書かれていても例外措置を設けている場合があり、早期入試を幅広く活用したい受験生には見逃せない点です。
高校の受験ルールとの整合性を確認
大学の募集要項で併願が認められていても、高校で独自の制限を設けている場合があります。
たとえば、指定校推薦を受けるなら他の大学の総合型選抜や一般入試を出願できないといった制限です。これは大学と高校の信頼関係を守る目的や、校内選考の透明性を維持するために設けられていることが多いです。
自分が応募したい学校推薦や総合型選抜がそうした校内ルールの対象に当てはまるかどうかは、事前に担任や進路指導の先生に相談しましょう。
高校の方針を無視して別の大学に合格した場合、入学手続きや卒業後の進路報告で問題が起きる可能性があります。大学側の要項だけでなく、高校のルールも合わせて理解することで、出願後に慌てずにすみます。
学校推薦と総合型の併願戦略とメリット
学校推薦と総合型選抜を併願すると、早期合格のチャンスを複数得られる利点があります。ただし、出願要件や対策内容がそれぞれ異なるため、効率よく準備する戦略が欠かせません。ここでは利点と注意点、出願プランの考え方を見ていきましょう。
両方を受けるメリットとリスク
学校推薦と総合型選抜の両方に出願すると、当然、合格するチャンスは増えます。
学校推薦は成績重視のケースが多く、日頃の定期試験や学習態度が評価されやすいです。
一方、総合型選抜では課外活動やプレゼン能力、将来のビジョンなどを強くアピールできるため、学力以外の面でも評価されやすいです。こうして複数の角度から自分を売り込める点が最大の魅力です。
ただしリスクとして、併願する分だけ書類準備や面接対策に時間を割く必要があり、両立の大変さを感じる可能性があります。
専願条件がある場合は、どちらか一方で合格すると他方を辞退しなければならないケースも生じます。また、学校推薦の中でも指定校推薦を利用するなら、合格後の進路変更がほぼできないことに注意が必要です。メリットとリスクを天秤にかけたうえで、自分の学習状況や将来像に合った出願方式を選ぶことが重要です。
得意分野を活かした出願プランの立て方
自分の得意分野を軸にした出願プランを立てると効果的です。評定平均が高く、学年順位が安定しているなら公募制推薦を狙いやすくなります。
クラブ活動やボランティアで成果を出している場合は、総合型選抜でプレゼンや面接時に具体的な経験を示すと大きなアピールポイントになります。大学や学部が求める人材像を調べ、自分の強みをどう結びつけるかを考えることが大切です。
また、大学ごとの入試方式や配点、面接内容を確認し、合格可能性を判断しましょう。
たとえば、英語外部試験のスコアを重視する総合型選抜があれば、TOEFLや英検のスコアを持っている受験生は有利になる可能性があります。
出願する学部の特色と自分の得意分野をうまく結びつければ、合格の確率が高まります。
必要書類とスケジュール管理のポイント
学校推薦と総合型は、一般入試と異なり準備する書類が多岐にわたることが多いです。推薦書や志望理由書、活動実績報告、調査書などを揃えるため、締切を把握して計画的に動く必要があります。
特に、評定平均が応募条件となる場合は、志望大学の基準を満たすかどうかを早めに確認し、必要に応じて成績アップに取り組むことが大切です。
提出書類には形式や提出方法の指定があることが多いため、募集要項を繰り返し読んで間違いがないようにしましょう。面接や小論文の対策日程と重なると焦りが生まれやすいため、以下のような一覧表で管理すると便利です。
| 大学名 | 出願方式 | 出願締切 | 面接日 | 合格発表 | 入学手続期限 | 条件(専願/併願可) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A大学 (公募推薦) | 学校推薦 | 9/30 | 10/15 | 10/25 | 11/5 | 専願 |
| B大学 (総合型) | 総合型 | 10/5 | 10/25 | 11/1 | 11/15 | 併願可 |
| C大学 (総合型) | 総合型 | 10/10 | 11/1 | 11/10 | 11/20 | 併願可 |
上記のようにまとめておくと、重複を避けながら必要な書類や面接準備を効率的に進められます。書類の作成には思いのほか時間がかかるため、夏休みごろから取りかかっておくと慌てずにすむでしょう。
一般選抜も視野に入れた受験計画の組み方
学校推薦や総合型選抜で早期合格を目指す一方、一般選抜に挑戦することで多様な選択肢を確保する受験生も増えています。ここでは、一般選抜と両立するメリットやスケジュール管理の方法、最終的な進学先を決める際のポイントを見ていきます。
一般選抜と併願するメリット
学校推薦や総合型選抜の結果が不本意だった場合でも、一般入試でリベンジができる点が大きなメリットです。
学校推薦や総合型選抜ばかりに力を入れていて、もしすべて不合格となった場合、浪人するとしても学力面でアドバンテージがない状況になってしまいます。
学校推薦や総合型で早い段階で合格を確保できれば、共通テストや個別試験にゆとりを持って臨めます。特に私立大学は複数日程を設定している場合が多く、試験日がかぶらない限り多くの学部を同時に受験できる利点があります。
また、早期合格が決まれば精神的な余裕が生まれ、苦手科目の克服や得点力アップにじっくり取り組むことができます。
入試日程と対策の両立に必要な準備
一般選抜に向けた勉強と、学校推薦や総合型選抜で求められる準備を並行して進めることはかなり大変です。
必ずカレンダーを作り、どの時期に何を優先するかを明確にしましょう。
現実的には、夏休みから秋にかけては学校推薦や総合型選抜で必要となる書類作成や面接対策にかなり時間が取られますので、一般選抜や共通テスト対策はそれまでにある程度余裕がある状態にしておくことが望ましいです。
秋以降に早期合格の結果が出たら、その合否を踏まえて一般入試の出願計画を固めます。もし早期に合格を確保できたなら、志望度の高い国公立や難関私立の一般選抜のみに集中して勉強することができます。
一方、合格を得ることができなかった場合は、一般選抜に向けて迅速に対策を進める必要があります。
一般選抜対策としてどのような勉強に取り組む必要があるのか、事前にある程度想定・準備し、すぐに取り掛かれるようにしておくことが大切です。
最終的な志望校選びの優先度を決める
複数の方式で合格を得る可能性がある場合、自分の将来像や学びたい分野を再確認し、どの大学を最優先とするかを事前に決めておくと迷いが少なくなります。専願条件のある大学に合格すると、他の大学の試験を辞退せざるを得ない可能性もあるため、第一志望と併願校の位置づけをしっかり整理しましょう。
大学の学部や学科によっては、研究テーマやゼミ内容が大きく異なる場合があります。オープンキャンパスや大学公式サイトのシラバスなどを活用して、カリキュラムに納得できるかどうかをチェックすることが大切です。特に専願で出願する学校推薦の場合は、合格後の進学が前提となりやすいため、本当に学びたい学問領域があるかを入念に確認しましょう。自分の志望度をあらかじめはっきりさせることで、合格後に迷うことなく、落ち着いて受験を進められます。
まとめ
ここまで、学校推薦型選抜と総合型選抜を併願する際の留意点や、一般選抜との両立方法をお伝えしました。最後に要点を振り返り、確実に合格を手にするために必要な情報収集やスケジュール管理の重要性をもう一度確認します。
併願で失敗しないための最終確認
学校推薦や総合型選抜は一般選抜よりも早い時期に合格がわかるため、メリットが大きい反面、専願条件があると進学先を自由に選びにくくなるリスクがあります。
合格後の辞退が認められる大学とそうでない大学を混同すると、結果的に第一志望をあきらめる事態になりかねません。募集要項やQ&Aなどを細かくチェックし、専願や併願の定義を理解したうえで出願計画を立てましょう。
また、高校で設定されている受験ルールも大切です。指定校推薦を得た場合は他の試験を受けられないことが多く、総合型選抜や一般入試との併願が禁じられるケースもあります。事前に担任や進路指導担当の先生に相談し、学校の内規と大学の募集要項を照合しながら、合格後の手続きまで見通しておくことがトラブル防止につながります。出願する大学が多いほど混乱しやすいですが、一覧表やスケジュール表を作っておけば、要点を見落としにくくなります。
早めの情報収集と計画が鍵になる
学校推薦や総合型選抜の要項は、一般入試よりも早めに公開されることが多いです。高2の頃から評定平均を意識した学習を心がけ、課外活動や英語試験などでアピール材料を増やしておくと、総合型選抜や公募制推薦の幅が広がります。大学ごとに評価基準や締切が異なるため、夏休み前には最新情報を収集し、対策スケジュールを組み立てましょう。
大学受験のマンツーマン指導ならレフィーにご相談ください
レフィーの大学受験コースでは
- 社会人プロ講師
- 東大、早慶以上の大学生・大学院生講師(かつ難関私立中高一貫校卒)
※さらに、プロ講師、東大早慶以上の大学・大学院生の中からどちらも採用率20%程度
が完全1対1のマンツーマンで指導するため、着実に効果を感じられるはずです。
「部活があって効率的に勉強しないといけない。レベルの高い先生に1対1のマンツーマンで自分のレベルに合わせて教えてほしい!」
「どうしても逆転合格しなきゃいけない。」
といった高校生は、ぜひお気軽に当塾レフィーにお問合せください!
通塾生の成績が実際に伸びています。
▼お気軽にお問い合わせください!
(横浜駅徒歩7分。原則対面授業ですが、オンラインをご希望の方はご相談ください)