「受験勉強しないとまずい状況だけど、雰囲気的に部活をやめづらい…」
「部活を最後まで続けてた人は合格して、途中でやめた人は落ちるみたいな噂があるってほんと…?」
「部活をしてたら全然勉強時間を確保できない!」
と思い悩む高校生はかなり多いのではないでしょうか。
本記事では、部活と大学受験を両立してきた先輩たちの実例を踏まえて、大学受験を目指すにあたって、部活をどうするべきか、また、両立のポイントをご紹介していきます。
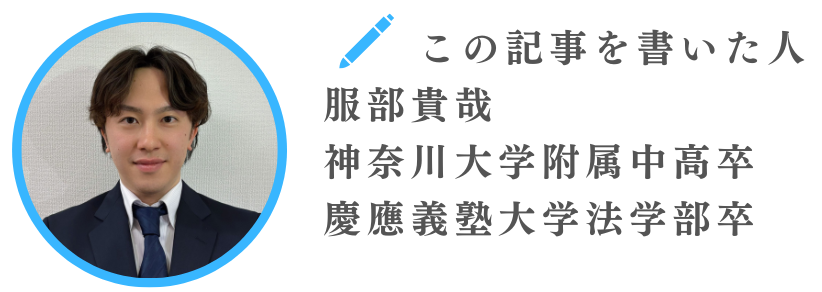
大学受験と部活の両立がベスト
大学受験と部活、どちらを取るかではなく、まずは両立を目指してみましょう。
両立には、さまざまなメリットがあります。
第一に、高校生活を自分らしく楽しみ、充実させながら学力を伸ばすことができる点が挙げられます。高校生活は勉強だけでなく、仲間とのコミュニケーションや集団活動を通して大きく成長できる時期です。部活をしっかりと続けることによって、学校生活そのものを充実させることができます。
また、部活で培う集中力や根気強さは、受験勉強にも良い影響を与えます。
高校生の部活動には競技やパフォーマンスでの勝ち負け、または成否が付きまといますが、そこに向かう過程で「やり抜く力」を培うことができます。
さらに、高校の部活を全力で行うことで、忍耐力やコミュニケーション力の向上、社会性の獲得につながり、大学受験の総合型選抜だけでなく、大学のゼミの面接、その後の就職活動、仕事においても大きく活かされてきます。
ペーパーテストがメインの大学受験でも、忍耐力があるか、努力ができるかという点は重要ですが、上記のようなソフトスキルは、社会にでてから、とても大きな役割を果たします。
部活を継続したことが評価される環境がある
大学受験をめぐる競争が激化している近年では、学力以外の視点が評価される場面が増えています。
推薦入試や総合型選抜などはその好例で、学力以外の部活経験や社会・課外活動が考査の大きな要素となります。
部活に真剣に取り組んだ経験のある生徒は、継続力や協調性を身につけていると評価される場合が多いです。
また、大学入学後も、自主的な研究やグループ学習などでコミュニケーション力が求められる場面が多くなります。部活でのチームワークや共同作業に対する理解がある生徒は、大学に入ってから円滑に人間関係を築きやすいと思います。
さらに、高校時代の部活で得られる喜びや挫折の経験は、感受性や思考力を深める契機になります。
自分のやりたいことを真剣に続けるうちに、「どうすれば効率良く上達できるか」「チームにとって最善の選択とは何か」といった問いを自然に考えるようになります。
こうした学力にとどまらない総合的な学習姿勢は、大学での研究やゼミ活動でも強みになりやすいです。
部活を続けるメリットとリスク
メリット①: 推薦入試で有利になる
部活動を続けた実績は、高校在学中の行動力や一貫した努力を示す材料になるので、推薦入試でアピールしやすいです。
活動実績として大会での成績があれば直接的に評価されることがありますし、リーダーとしてチームをまとめた経験などは面接や小論文で強いアピールポイントになります。
たとえ表彰された実績がなかったとしても、複数年にわたり地道に活動を続けた姿勢そのものが、「忍耐力がある」「継続力に優れている」人物であることを示す根拠になり得ます。
総合型選抜や公募推薦などであれば、書類やプレゼンテーションで部活経験を具体的に表現できます。日頃の練習内容やチーム内での役割、学習との両立に工夫した点などを整理しておくことが大切です。
推薦入試では調査書の評定平均や出欠状況だけでなく、部活動や生徒会活動、ボランティアなどに力を入れていたかも重視されることがあります。
部活を継続することで学校生活全体を充実させた生徒は、総合的に好印象を与えやすいです。
メリット②:応用できる体力と精神力
部活を継続して得られる体力と精神力は、大学受験の大きな武器になります。
日々のトレーニングや練習を地道に重ねることで基礎体力が向上すると、長時間の勉強においても疲れにくくなります。
実際に高校生の中には、暗記学習や苦手科目を粘り強く克服できたのは、長距離走などで鍛えた忍耐力があったからかもしれないという声もあります。
学校の先生や塾の先生も、部活動を引退まで頑張った生徒の中には、その後の伸びがすごい生徒がいると実感しています。
また、部活の練習や大会に臨む過程では、失敗や挫折を経験することもあるでしょう。
たとえば、思うように成果が出ずに悩んだり、チーム内で意見が合わずに衝突したりする場面で、困難を解決しようと試行錯誤する姿勢が身につきます。
このような経験があると、受験勉強でネガティブな気持ちになったときや、模試の結果が思わしくなかったときに、気持ちを立て直すことができるでしょう。
さらに、目標を立て、それに向けて毎日努力した経験は、大学合格に向けて着実に毎日の勉強をこなす時に活きてくるでしょう。
リスク①:勉強時間をどうやって確保するか
部活と受験を両立する最大のハードルは、何より勉強時間が不足することです。
朝練や放課後の練習があると、帰宅する頃には夕方から夜になり、十分な学習時間を確保しにくくなります。特に土日にも試合や大会があるスポーツ系の部活の場合は、まとまった勉強時間を取りづらいと感じる人が多いです。
この時間不足を補うためには、通学時間や休み時間などのスキマを有効活用することが重要になります。常に単語帳や社会のプリントなどを持ち歩き、ちょっとした移動の合間に勉強できる体制を整えましょう。
また、自分にとってベストな勉強ルーティーンを早めに確立することも大切です。
毎日のように「今日はいつなにを勉強しようかな」と考えているようでは絶対にいけません。
それを考えている時間がもったいないですし、そもそもそれを考えている時点で、大きな受験本番までのスケジュール、学習計画を立てられていないことになります。
いち早く勉強のルーティーンを作り、できるだけ作業的に日々の勉強をこなすことができるようにすることを目指しましょう。
リスク②:疲労やモチベーション低下
部活と勉強の両立を続けていると、どうしても疲労が溜まります。
夜中まで受験勉強を頑張ろうとしても、部活で消耗した状態では集中力が続かず、思うような成果が上がらないでしょう。
また、モチベーションの低下も大きな課題です。部活と勉強の両方に注力すると、どちらか一方がうまくいかないときに大きなストレスを感じる人が多くなります。たとえば、練習試合が続いて疲れてしまい、勉強への気持ちが向きにくくなることがあるかもしれません。逆に、勉強が手につかず成績が思うように伸びないときに、部活すらも義務感で行ってしまうという悪循環が生じることがあります。
これらの疲労やモチベーション低下を回避するためには、週に一度はしっかりと休憩、リフレッシュ時間を設けることが大切です。
完全に気持ちをリセットできるような休息を取り、趣味の音楽を聴く、友人と少しだけ会話を楽しむなどを取り入れると良いです。
ダラダラするだけというのは、意外にもリフレッシュにならないことが多いので、自分の好きなこと、その瞬間に没頭できることに時間を使いましょう。
また、身体のケアや軽いストレッチも習慣化しておきましょう。
部活と両立して現役合格した先輩から学ぶポイント
ポイント①部活が終わった後に期待せず、早くから勉強を始める
がっつりと部活に打ち込んでいる場合、高3の夏休みごろに部活を引退するケースが多く、「今はがっつり勉強できないけど、部活が終わったら切り替えてがっつり勉強しよう」と考えている人も多いでしょう。
これはこれで間違いではありませんが、このように後回しにする意識だと、現役での合格には間に合わない可能性があります。
部活と勉強を両立し、現役合格を果たした先輩は、部活引退後はもちろん、引退前から出来る限りの勉強を進めているように思います。
英単語や古文単語など、暗記がメインになる学習は高1・高2の段階から少しずつ積み重ね、長期休暇のたびに、塾の講習に通って苦手分野を克服したりと、早い段階から受験に向けて動き出していることが多いです。
部活をやっている人ほど、早めから大学受験に向けて動き出すことが大切です。
ポイント②引退後の集中力アップ、勉強時間増加
部活を続けていると、どうしても体力的な疲れから勉強に集中できないこともありますが、部活引退後は、むしろその体力を活かして、毎日長時間集中して勉強することができます。
現役合格を果たした先輩たちは、部活引退後に凄まじい追い込みをすることができたはずです。
部活を引退し、少し浮かれてダラダラしてしまうことがないよう、部活を引退したら、すぐさま本気で受験勉強に取り掛かることができるように準備しておきましょう。
ポイント③学習計画・スケジュール管理で差をつける
部活と大学受験を両立するということは、当然、部活動をしていない受験生と比べて、勉強に充てることができる時間は限られています。
そのため、限りある勉強時間を最大限有効活用しない限り、ライバルに差をつけられてしまいます。
勉強時間を有効活用するためには、志望校と自分の現状の学力に合わせて長期スパンの学習計画を作成し、それを1日単位のスケジュールに落とし込む必要があります。
必要なことだけを正しい順序で学習することで、時間を有効活用しましょう。
自分の判断に自信がなければ、塾の先生や学校の先生に相談し、一緒に学習計画を立てても良いでしょう。
ポイント④授業を有効活用する
ただでさえ部活動で、自学自習の時間を取りづらいため、学校や塾の授業時間を最大限活かす必要があります。
せめて授業時間は、部活動がない人と差をつけようというレベルの意識が求められます。
以下の点を意識しましょう。
- わからないことがあったら、すぐに先生に質問して解決する
- 暗記すべきことは、授業中に覚えられるよう、その場で紙に書いて覚えたり、必要があれば語呂合わせを作る
- 授業中に隙間時間あったら、その間に暗記系の勉強をする。もしくは類題を解いてみる。
- 学校によっては、自分の大学受験には全く関係ない授業を受けなければいけない状況があるが、もし許可されるのであれば、その授業を取らない。どうしても取らなければいけない場合は、授業中に勉強してもよいか先生に相談してみる。
ポイント⑤スキマ時間を活用するコツ
絶対にスキマ時間も活用しましょう。
電車に乗っている時間、授業の合間の休憩時間、トイレに行っている時間、徒歩で移動している時間、など、勉強することができる時間はたくさんあります。
歩きながら数学を勉強することは難しいかもしれませんが、リスニングであれば勉強できます。
「少しでも時間があるなら勉強する!」という意識が最終的にかなり大きな差につながります。
ポイント⑥自分に必要なことだけをコンパクトに学べる環境を選ぶ
部活動をしていると、時間帯の都合で他の受験生が受講できているはずの予備校・塾の授業を受けることができない、また、授業を受けていると自学自習の時間が足りなくなってしまう、といったことがあるはずです。
そして、部活動を高3の夏ごろまで続ける方の多くは、他の部活動をしていない受験生よりも、勉強が遅れをとってしまっている(成績が相対的に低い、満足のいく合格判定をもらえていない)でしょう。
これらのことから、部活と大学受験の両立を目指す受験生は、自分が受けられる時間帯で、自分に必要なことだけをコンパクトに学ぶことができる環境、つまり、個別指導塾、家庭教師、オンライン講座が最適な環境だと言えるでしょう。
自分に必要なことだけをコンパクトに身に着けることができる環境で、最短最速で学力を伸ばすことを意識しましょう。
まとめ
部活と大学受験を両立するには、計画性やスキマ時間の活用、そして早期スタートの意識が不可欠です。
部活を続けることには、推薦入試でのアピールや体力・精神力の養成など、大きなメリットがありますが、勉強時間の不足や疲労、モチベーション低下といった課題もあります。
これらを克服するためには、日々の学習習慣を細分化し、部活のスケジュールに合わせて調整するといった細かな工夫が大切です。
「志望校に合格したいが、まだ部活を続けていても大丈夫なのか」
「部活は続けようと思っているが、志望校に合格したい。一緒に学習計画を立ててサポートして欲しい」
と言う方はぜひ当塾LEFYにお問合せください。
■関連記事
早稲田大学は難しすぎ!?偏差値や難易度、難しい理由を合格者が解説
東大・早慶・上智の4年間の学費!免除・補助を受ける方法も解説!
【大学受験】早稲田・慶應の過去問はいつから何年分取り組む?
大学受験のマンツーマン指導ならレフィーにご相談ください
レフィーの大学受験コースでは
- 社会人プロ講師
- 東大、早慶以上の大学生・大学院生講師(かつ難関私立中高一貫校卒)
※さらに、プロ講師、東大早慶以上の大学・大学院生の中からどちらも採用率20%程度
が完全1対1のマンツーマンで指導するため、着実に効果を感じられるはずです。
「部活があって効率的に勉強しないといけない。レベルの高い先生に1対1のマンツーマンで自分のレベルに合わせて教えてほしい!」
「どうしても逆転合格しなきゃいけない。」
といった高校生は、ぜひお気軽に当塾レフィーにお問合せください!
通塾生の成績が実際に伸びています。
▼お気軽にお問い合わせください!
(横浜駅徒歩7分。原則対面授業ですが、オンラインをご希望の方はご相談ください)
LEFY公式ラインでは、中学受験/中高一貫校生の勉強/大学受験に関する情報を配信しています。
LEFYマガジンの記事を定期的に通知していますので、ぜひご登録ください!
